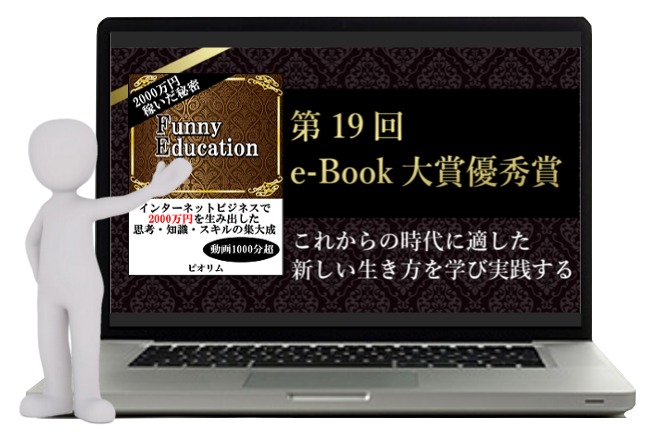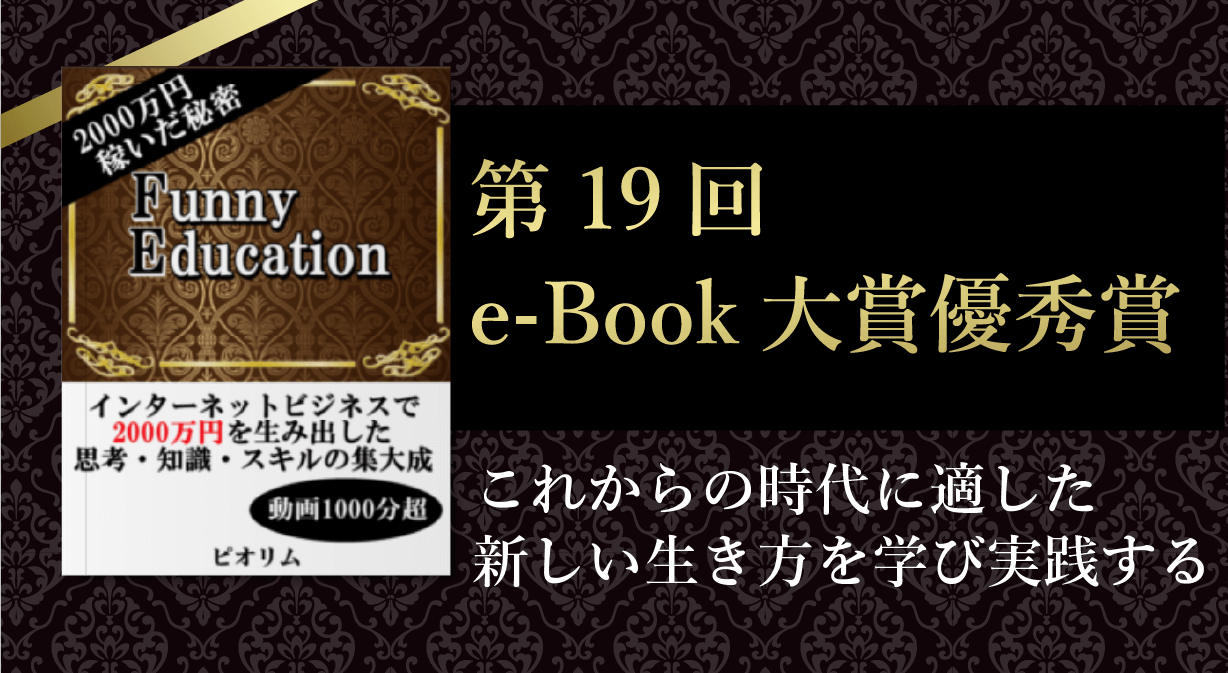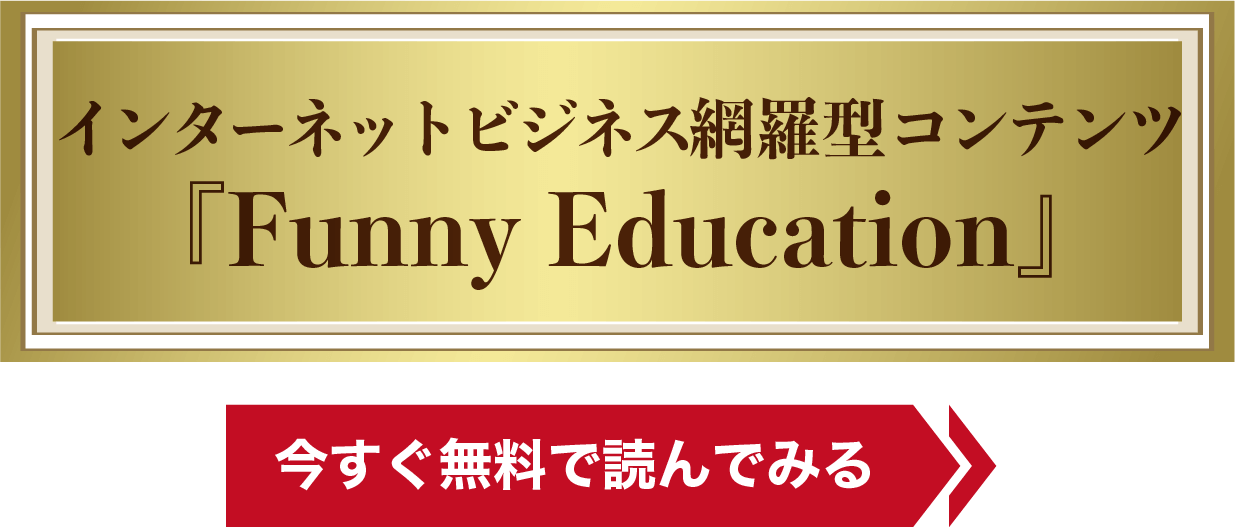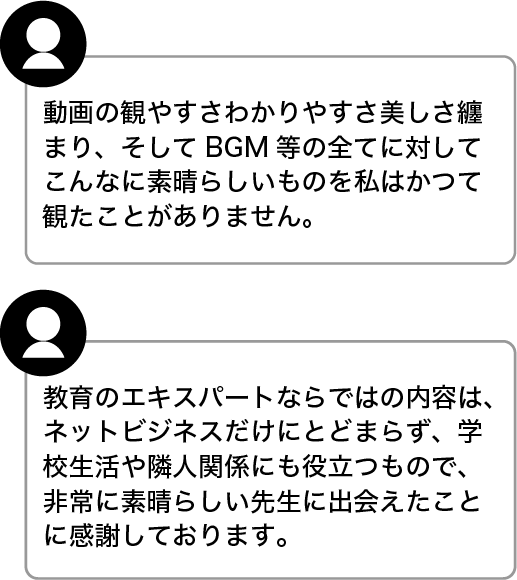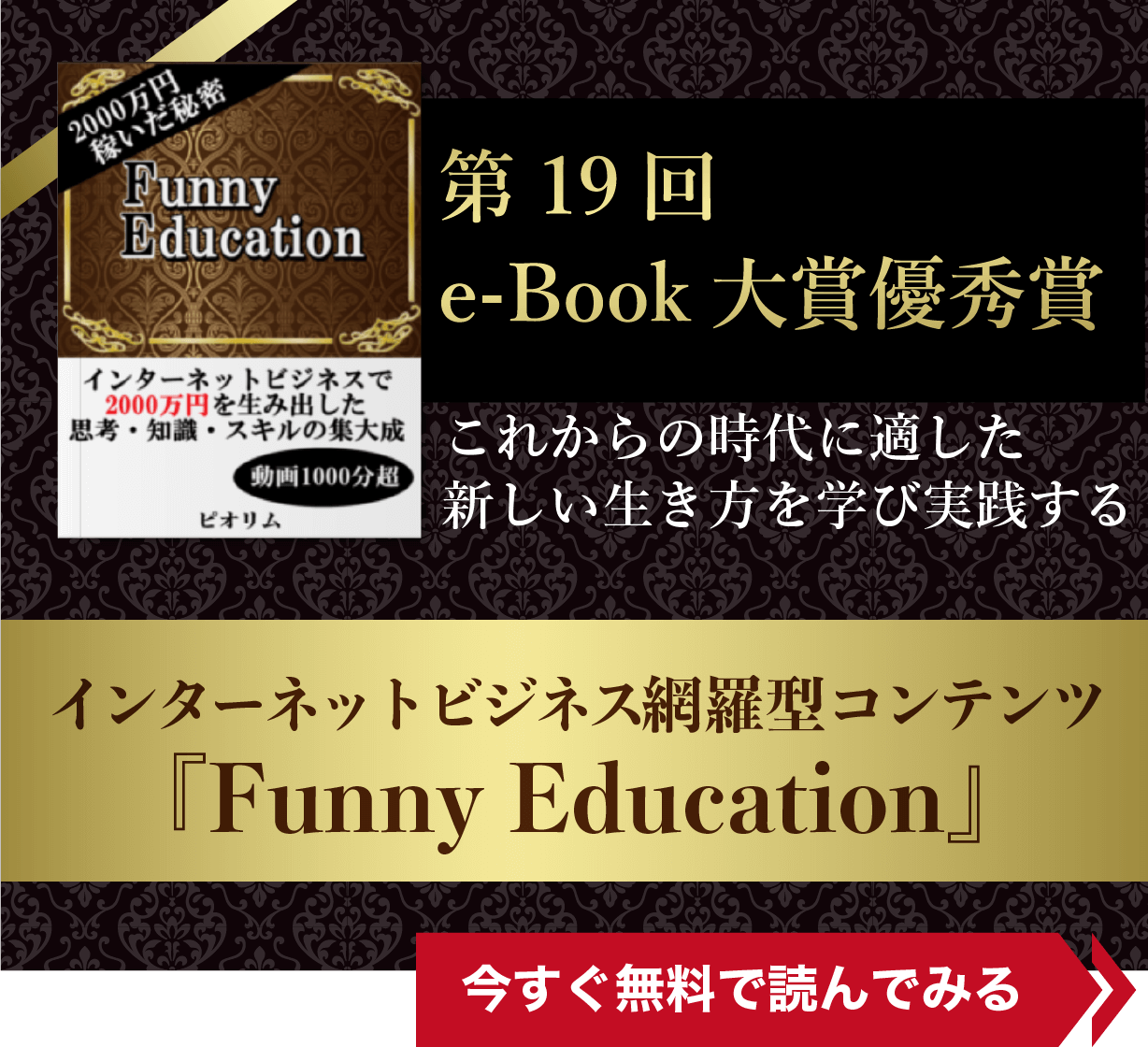ここで言うマーケティングとは、大雑把に言えば「自分のビジネスのターゲットを選定してから、その人たちに商品やサービスを購入してもらうまでの一連の流れ」のことです。
◎「どんな人に価値を提供していくか…」
◎「自分の商品・サービスの存在をいかに多くの見込み客に知ってもらうか…」
◎「どのような手段で商品・サービスの魅力を伝えていくのか…」
◎「価格はいくらに設定するのか…」
◎「どのような方法で販売していくのか…」
などなど、ビジネスにおいては自分の商品を買ってもらうまでに様々なことを考え、工夫を施していくことになります。そしてこのように工夫を施したうえで商品を販売する、その戦略のことを“マーケティング戦略”と言います。
そして当然、どのようなマーケティング手法が望ましいかは、時代の変遷とともに変わってきます。時代の流れにともなって市場の性質が変わってくるので、有効となるマーケティング手法も変わるというのは当然のことです。
時代を越えて普遍的に通じるマーケティング手法など存在しません。「ある時代に成果を上げていた手法が、いまや有効に機能しなくなってしまった」なんてことは、ごくごく当然に起きるのです。
では、今の時代のマーケティングには何が重要になるのか?
そこで今回はまず、今の時代のマーケティングを考えていく上での前提となるかつてのマーケティング「4P」「4C」について、それがどういった理論なのかをマーケティングの歴史と併せて解説していきましょう。
販売者視点のマーケティング「4P」とは?

マーケティングにおける「4P」というのは、1960年代にアメリカの経済学者エドモンド・ジェローム・マッカーシーが提唱した理論です。
そこでの「4つのP」というのは次の要素になります。
①Product(製品)
②Price(価格)
③Place(流通)
④Promotion(プロモーション)
つまりこの理論では、市場を細分化して顧客のターゲットを決めたら、
②適正な販売価格を決定し、
③その商品が顧客の手にわたる流通手段を決め、
④効果的にプロモートをかけて販売していく
この4つをマーケティングでの重要な要素としているのです。「①何を、②いくらで、③どういった経路で、④どのように販売するか」という4つですね。
ちなみに、ここでの「Place(流通手段)」というのは、直営で販売するのか・代理店で売るのか・自ら訪問販売をするのか、といった「顧客の手に商品を届けるための手段」と考えればOKです。そしてこの流通手段によって「商品の適正な価格」も変わってくるので、②と③の順番に関しては一概には言えないところがあります。
さて、この「4P」の考え方はしばしば“売り手側の視点”ということが言われます。これは「商品開発」も「価格決定」も「流通経路決定」も「プロモート」も、すべて販売者側のロジックだけで決められているからです。
もちろん顧客のニーズも考えてはいるものの、この「4P」はどちらかと言えば「自分が良いと思うものを作る」という販売者の視点を優先した考え方です。
このように、販売者側のロジックを優先させる方法を、マーケティング用語では「プロダクト・アウト」と言います。
当時このような手法をとっていた背景には「良いものを作れば売れる」という時代があったのです。
顧客視点のマーケティング「4C」とは?

そんな中、1990年代に入ると、市場にはさまざまな商品があふれかえるようになります。
販売者は良いと思った商品を作ってどんどん提供していくわけですから次第に商品の数も増えていき、「飽和」といった状態になります。需要と供給のバランスが崩れ、供給過剰の状態になってくるのです。
すると、これまでと同じように販売者側の視点を優先しただけではなかなか商品を売ることが難しくなってきました。
そして次第に「4Pは時代遅れ!これからは顧客側の視点に立つべき!」ということが言われるようになります。販売者視点ではなく“顧客の視点”に立って商品を開発することの重要性が謳われるようになったのです。
そのようなことを謳う典型的人物がロバート・ラウターボーンという学者です。彼はこれまでの「4P」に代わる理論として「4C」というものを提唱します。
ここでの4つのCとは以下の通りです。
①Customer Value(顧客価値)
②Customer cost(顧客のコスト)
③Convenience(利便性)
④Communication(顧客とのコミュニケーション)
・“顧客にとって”その商品はいかに価値があるものか…
・“顧客にとって”いかにリーズナブルな価格か…
といったことを重視し、それまでの「4P」の販売者視点の理論を顧客側の視点から再定義しなおしたのです。「販売者が何を作ったかではなく、消費者がどんな価値を享受できるのか」という考えが重要になったわけです。
このように、顧客側の視点を優先させて商品開発等をしていくことを「マーケット・イン」といいます。
現代におけるマーケティングは…
時代の変遷に伴い、マーケティングの考え方も従来の「プロダクト・アウト」から「マーケット・イン」へシフトしてきました。販売者視点よりも顧客視点を優先させることで、ものがあふれた時代でも一定の需要は確保できるようになったのです。
しかし、現代ではこれすらも通用しないような現状があります。
その理由は、ある程度物質的に満たされた現代においては顧客自身も自分の欲求や悩みを明確にできなくなってきているからです。
世の中にいろんな商品が溢れかえると、人が何か悩みを抱えていてもそれを解決できそうな商品はもう市場に多く出回っていることになります。いわば悩みがあったとしても、既存の商品やサービスですぐに解決できそうなのです。
そのような状況の中では、顧客の側も「今何がほしいのか・何に悩んでいるのか」を明確にすることができなくなりがちです。販売側が「顧客のニーズに合わせて商品を開発する」といっても、そもそも顧客の側がニーズをはっきりと言えないのです。
もちろん、これは人々が今の状況に完全に満足しているというわけではありません。ただ、これまでなかった新しいモノが増えすぎてしまったため、これ以上の欲しいものをうまく言語化できない状態になったということです。
人の欲求や悩みが顕在化されていない以上、それに合わせてものを作ることなどできません。今の時代は「4C」という理論でも困難になってきているのです。
では、それを踏まえた上で、現代ではどのようなマーケティングが有効になってくるのか…?
メールマガジンの中では、インターネットを活用したビジネスで大きなお金を生み出すにあたって必要な知識やそのための具体的手順を、限定公開動画と併せて提供しています。これから自分のビジネスで(自分自身の力で)お金を生み出していきたいということをお考えの場合は、ぜひ無料メルマガでの情報も受け取ってほしいと思います。
⇒メールマガジン登録ページへ